
量子スポーツコンディショニング:ケガ予防とパフォーマンス向上を根本から変える!
スポーツ界に革命をもたらす「量子スポーツコンディショニング(QSC)」をご紹介します。量子の振動技術と波の性質を活用し、アスリートの身体コンディショニングを高精度に最適化することで、ケガの予防とパフォーマンスの最大化を実現します。
はじめに:量子技術が拓くスポーツの新境地
量子の概念が誕生して100年以上が経ちますが、特にここ数年で、「量子(力学)」という言葉を耳にすることが増えてきました。ニュースでも量子コンピューターが話題となり、物質の最小単位である素粒子の粒子・波の二面性などの性質を活用した技術として注目を集めています。また、医療分野でも**振動医学(バイオレゾナンスメソッド)**として、ドイツをはじめとした先進各国で研究が進められ、技術が蓄積されています。一方、スポーツ分野では過去に活用例はあるものの、まだ一般的ではありません。しかし、これから研究が急速に進み、今まで抽象的な言葉で表現されていた身体の機能やパフォーマンスのメカニズムが、量子技術によって解明されていくでしょう。
私は施術家として22年以上の経験を積む中で、出会った90%以上の人が手足などの筋力低下を起こしているという事実に驚きました。日本のトップアスリートを見ても、手足の筋力はほぼ低下状態にあると感じています。これでは、ケガも増え、パフォーマンスも十分に発揮できないという実感を抱いています。
病気や症状に苦しむ人が増加の一途をたどる中、スポーツ選手も同様にケガや故障が多発し、思うように成績が残せなかったり、選手生命を絶たれたりするケースも少なくありません。このような状況を目の当たりにし、元々企業で分子・原子レベルの分析・研究をしていた私の研究者魂に火がつきました。結果が出ていないということは、原因の見方や方向性が違うのではないか?何事も本質的な点から考えていかなければ、根本的な問題は解決しないと考えました。
筋力低下やケガ・故障、パフォーマンス、身体バランスがどの様に密接に関連しているのか、そして物質の根本的な物性(量子、振動など)で何か改善できないかの研究が始まりました。そして今回、その研究の成果として『量子スポーツコンディショニング(QSC)』という独自のコンディショニング技術が誕生しました。これはとてもシンプルで、どんなタイプの人にも同じ手法でできる万能な技術です。
QSCの3つのポイント
- 量子技術を活用した、高精度な身体コンディショニングの最適化 量子の振動技術と波の性質を利用し、まず身体バランスを整え、機能を正常化します。
- 最適化された状態の維持 ①メンタル、②道具・靴・サプリメントなどの物、③構え・フォーム・動作など技術面を調整し、最適な状態を維持します。
- 最適化できたことの評価手法の可視化 身体が整ったかどうかを、**筋力テスト(人間が持つ高精度のセンサー)**を使って評価します。これにより、今まで選手の感覚に頼ってきたものを、筋力という客観的な指標(体感+目視)で確認できるようになります。
従来の治療・施術分野では、西洋医学と東洋医学、医師や理学療法士、鍼灸、整体、カイロプラクティック、気功などのエネルギー療法など、分野が多岐にわたり、その良し悪しを比較評価することは非常に困難でした。また、道具・靴などでも専門知識が必要なため、どうしても提供者側が主導になりがちです。このように、専門知識が必要な領域には、選手や指導者が踏み込みにくい壁が存在すると考えられます。インターネットの発達により世界中の情報が簡単に入手できる反面、何が良くて何が悪いのか見極めることが非常に難しい時代です。QSCの評価法は、これを公平な目で自分でも見極めることを可能にします。
今回のご提案は、量子技術をスポーツ分野に取り入れ、しかしながら人間にしかできない良さは残し、スポーツの新しい可能性を創造する取り組みです。自分が今までしてきた経験だけで物事を判断するのが非常に難しい社会ですが、固定観念や先入観を横に置いて、自分の身体・メンタル・道具・動作技術を検証し、スポーツ人生をより有意義にしていただきたいと思います。まずは頭と身体で体感し、身体の感覚やプレーの違いを実感していただき、今後の選手として、また指導者としてのスポーツ人生に活かしていただけましたら幸いです。
量子とは何か?その本質と応用
量子の定義と特徴
私たちの体や物など地球上(宇宙)にある物質は全て原子が集まってできています(原子同士がつながると分子になります)。原子の中には原子核があり、原子核の中には陽子と中性子が、その周りには電子があります。陽子と中性子の中には、アップクォークとダウンクォークがあり、電子と合わせて素粒子と呼ばれます。素粒子には、フォトン(光子)など17種類があり、これ以上小さく分解できない物質の最小単位です。原子から素粒子まで、これらの小さい物質が「量子」であり、量子力学という独特の物理法則に従います。
量子の代表的な特徴は、粒子と波動の二面性を持つことです。光は粒でもあり波でもあります。また、観測者効果では、波の状態だった光が、人が観測した瞬間に粒に変化することが確かめられています。これは、人間の意識・意図が、物質・物に何らかの影響を及ぼしたと言えます。意識の状態によって、身体から出ている波動(周波数)が変化し、その波動が物質の状態に影響したと理解できます。意識についてはまだ完全に解明されていませんが、近い未来には量子力学で意識も解明される日がくると思われます。量子力学が誕生して100年が経ちますがまだ完全には解明されておらず、また宇宙や脳も5%しか解明できていないと言われることからも、人類はまだまだ発展途上段階にあるようです。しかしながら、量子の全容が解明される前に、既に私たちの日常で技術は活用されています。今回の「量子スポーツコンディショニング」も、技術的には基礎はできており結果を確認することができています。今後は、この結果が量子の解明とともに理論的に数値化されていくものと考えています。
量子は極めて小さく、その振動の様子も見ることはできません。そこから出る波(波動、周波数)も見える波と見えない波があり、周波数帯で区別されています。私たちの目には可視光線帯という限られた範囲の物だけを見ることができます。赤、青など周波数の違いで違う色に見えます。一方、私たちは日常から目に見えない物を沢山利用しています。携帯やテレビなどの電波、病院に行けばX線などを活用していますし、紫外線や赤外線、放射能なども見えないけれど存在することを知っています。音も空気の振動を耳でキャッチして認識することができます。見えない物はどうしても受け入れがたいかもしれませんが、私たちはその影響を受けたり与えたりして生活しています。
量子テクノロジーの応用実例
量子の粒と波の二面性以外にも、「量子重ね合わせ」「量子もつれ」「量子トンネリング」「量子テレポーテーション」など様々な現象があります。これら量子テクノロジーは、私たちの身近なところでは半導体やMRIなどで既に活用されています。その他、量子計測・センサー(高精度測定)、量子通信(安全性)、量子シミュレーション(新素材・物質開発)などがあり、量子コンピューターはまだ発展途上段階です。
医療分野への応用実例/振動医学(波動医学)
人体の最小単位は細胞という認識が一般的ですが、細胞は更に分子、原子、素粒子と細分化できます。その素粒子などはそれぞれ物質特有の周波数で振動しています。周波数は、1秒間に振動する回数のことで振動数とも言います。人間の臓器や部位もそれぞれ固有の周波数を持っており、その周波数が乱れると様々な不調をきたします。脳波や心電図なども、波として観測できます。周波数を整えて自然治癒力を引き出し体の健康を整える手法を**バイオレゾナンスメソッド(生体共鳴法)**と言い、ドイツをはじめ世界各国で活用されています。日本でも、この振動技術が医師や歯科医師、代替医療の現場で活用されています。現在、私の施術院でもその振動技術を使った施術で良好な結果を得ています。最小単位の見方の違いが、今の病気の増加に繋がってしまっているとすると、医療分野にも、生物学だけでなく、物理学など総合的な科学の必要性を感じます。
スポーツ分野への応用実例(既存)
- 量子AIによる、ポジショニングや動きなど戦術の最適化(サッカー、バレーボールなど)
- 量子力学の「重ね合わせ」を活用して、バスケットボール選手がパスかシュートかの選択をパラレル処理で瞬時に行っていると言う研究など
スポーツ界の現状と課題:QSCの必要性
スポーツは人々に感動と勇気など精神的な良い影響を与える一方で、プロ選手や実業団選手にとっては過酷な職業でもあります。選手寿命は種目にもよりますが30~40歳位(ゴルフなどは長い方ですが)、近年は医療や身体ケアの技術向上などで選手寿命は長くなる傾向にあります。しかしながら、選手のピークは短く、その間にいかに「ケガをしないか」「自分の能力を最大限に発揮できるか」ということが、現役時の成績や選手寿命だけでなく、引退後のセカンドキャリアにも大きな影響があり、人生を左右すると言っても過言ではありません。また、技術的な向上だけでなく、人間性の成長も現役時のみならずセカンドキャリアにも影響し、どのチームに所属するか、指導者やチームメートなどだれと出会うか、自分の努力と同時に、運やツキのような要素も大切になります。
幼少の頃からトップアスリートを目指してスポーツに励み(家族の協力も)、スカウティングも小中学生の頃から着目されて、どこの学校に行くかを決め、技術の向上と成長期の体づくりや過度な身体への負担など相反する要素も存在します。年々進歩する技術の高度化と身体バランスの低下の促進と並行して、故障の若年化も問題になっています。
一方、アスリートの活躍の場はオリンピックやワールドカップ(世界大会)などの国際大会だけでなく、レギュラーシーズンから海外で活躍する選手も増え、日本人の技術レベルも年々向上していると言えます。国もスポーツ庁を設置し、各競技ごとに強化策も行われサポート体制は充実してきていますが、競技によって世界との「差」は存在するところです。
「差」とは何か?
外国人は身体能力が高いと言いますが、「体の大きさ(身長・体重・手足の長さ=パワーなど)」「動き(俊敏性スピード・跳躍など)」など優れていることもあれば劣るところもあります。近年は、アジア選手も身体の大きさは近づいていると感じます。また、身体以外の要素として、「メンタル」では国民性や育ってきた環境も影響があるでしょうし、「コンディショニング」「トレーニング」「バイオメカニクス」でも国による相違があったものが情報社会や国際交流で差がなくなり、「道具」開発ではその国のメーカーの技術力が物を言いますが選手の選択にゆだねられていること、「戦術」「情報データ」ではチームや指導者・アナリストの能力や見方によって違うこと、「指導者」も国際化していることで差がなくなってきていること、など身体能力とは違う部分も多々あります。こうして見ると、これらの「差」は確実に縮まってきており、これらの優劣をトータルして戦うこと、長所を生かすことで勝敗が逆転することも起こります。
現状を見ていると、トレーニング法、フォーム(バイオメカニクス、動作解析)、データ情報、道具の開発など=ソフト面が注目されていますが、本来の主体である身体(心)=ハード面のコンディショニングがあまり深く追求されていないのではないでしょうか。もしかしたら、身体の準備不足(コンディショニング不良)のまま、トレーニングやプレーをするので、当然ケガも起こりやすくなり、パフォーマンスも出にくい悪循環が起こっている可能性があります。
結論としては、物理的にカバーできない部分を除いて、パワー・俊敏性・跳躍など身体に関する能力と、メンタル・トレーニング技術・バイオメカニクスなど身体能力向上のための手法に関すること、道具・データ・戦術など身体以外のこと、このレベルを今よりも上げていくことが大切になります。そのレベルを上げるのに、どうしたら良いのか?私見ですが、「メンタル」と「バランス」が鍵を握るのではと思っています。スポーツは人間がすることであり、その主体である人間の心身が主役です。思考と言動の発信元であるメンタル、それを受けて言動する身体のバランスが一番大切な基礎ではないでしょうか。進化したメンタル技術と、新しいコンディショニング技術の発展がスポーツを大きく変える予感がしています。それをサポートしてくれるのが、今回着目している量子技術です。
アスリートに求められる2つの要素
アスリートに求められる(求める)ものは、大きく次の2つであると思います。
- ケガをしないこと(予防、回避、早期回復)
- 能力を最大限に発揮すること(潜在能力、発揮の仕方)
このためにスポーツ選手(またはチーム)は、身体のケアや治療などメンテナンスをする「フィジオ、アスレチックストレーナー」と、身体能力を向上させる「フィジカル、ストレングストレーナー」をつけているのが一般的です。
ケガの予防について
連日、プロやトップ選手のケガのニュースを目にします。シーズン終盤や避けられないケガならまだしも、開幕前(キャンプ)や開幕早々のケガも多く、長年活躍すると勤続疲労と言われます。オフが短すぎて十分にケアができないのか、ケアしているけれどそれ以上に負荷を掛け過ぎているのか、技術の進歩で負荷が増えているのか、動作中のケガもあれば、衝突など外的な要因もあり、選手の能力によって避けられるケガと避けることができないケガもあると思われます。よく記事などで、ケガをしないために鍛える・強化する・トレーニングする、ケガをしない体づくりをするなどコメントがあります。では、ケガをしない(減らす)ためには何をどうすれば良いのでしょうか?球数制限などの対策は根本的な解決になるのか、手術をすれば解決できるのか、ケアなのかトレーニングなのか。
ケガが減らない現状を見ると、ケガ故障の原因とメカニズムの解明、その対策の分析と評価、見直しが早急に必要かと思われます。起こったケガに対処するのも大切ですが、起こらないように予防することが更に重要になると思います。
よく耳にするケガの種類:
肉離れ、脇腹の痛み、疲労骨折、靭帯の損傷(肘のトミージョン手術、膝)、肩の損傷、その他スポーツ障害多数 ※上肢や下肢のコンディショニング不良、違和感、張りなど、具体的にどこがどうなっているのか、本人にしかわからない感覚や関係者以外把握しにくい表現もあります。
それぞれのケガ故障が起こる原因とメカニズムの解明が大切で、それに対して対策をすることでケガ故障を減らすことに繋がります。
ケガを起こりやすくする原因、可能性:
- 身体への負担の増加(メカニックやトレーニング技術向上で、スピードやパワーが増)
- コンディショニング不良(準備不足)
- 道具や靴の影響(合っていない)
- フォーム、動作の不良(悪いフォーム、体の使い方)
- メンタルの影響など
ケガの予防をどうやってするか:
まず、主体である「身体」「メンタル」(ハードウエア)からみていきましょう。 身体のバランス(歪み)を整え、身体機能を正常化することで、
- 負荷の分散:骨格(関節)の位置を調整、筋バランス調整(強弱、左右内外前後差なくす)
- 弾力性の向上:血流の改善により腱・靭帯・血管などの弾力性向上
- 動作の改善:安定したフォーム、再現性向上、動きが良くなることでケガを回避できる ※ケガの早期回復、疲労回復には血流の改善が有効
メンタルの状態と身体バランスの崩れ(筋力低下)を理解、体感、記憶することで、
- メンタルによる身体バランスの崩れ(歪み)を軽減する
次に、副体である「道具・靴・サプリメントなど」(ソフトウエア)をみていきましょう。 道具、靴などによる身体バランスの崩れを防ぐ、
- 身に着ける物(アクセサリー類など)、道具、靴、サプリメントなどを最適化 →最初から合うものを採用していく、合うものを開発していく
一般的に行われていること:
- コンディショニングに関して
- ソフト面の充実、ハード面の聖域(専門知識) ソフト・副体:心身以外の物や技術が発展、注目されている →トレーニング法、道具の開発、情報データ数値化、動作解析など これらはあくまで付属のことで、いくら発展しても根本解決には至らず、人間本体が良い状態にあることが大前提です。しかしながら、大切なことであることは間違いありません。効果を、能力(数値、記録など)で確認するだけでなく、身体バランスや筋力変化なども評価して確認する作業が必要と思われます。 ハード・主体:心身 →治療・施術・メンテナンスなどのコンディショニング、メンタルトレーニング 医療知識など専門性が高く、選手や指導者が入り込みにくい領域になっていないか(そのため一度チームや選手に入り込むと変更が少なく、切磋琢磨がなくなり、コンディショニング技術の進歩が妨げられる)。医師や施術側が提案したことを受け入れるしかないのでは(正解であれば問題なし)。施術方法は様々あって良いと思いますが、施術後に効果を公平に評価できる手法があれば良いのではないでしょうか(施術方法の違い、施術者の違いがあっても効果が分かる)。そうすれば結果で判断でき、様々な議論が風通し良く交わされ、全体的なレベルも上がって、選手の皆さんのためになるのではないでしょうか。
- 手術の是非 もちろん、手術が必要なケースも多々あるかと思います。しかしながら、手術以外の方法が最良なケース、手術しなくても済むケースがないかどうか吟味してみるのも必要かと思います。なぜなら、メスを入れることは、皮膚や筋肉など軟部組織を切断することになり、当然それによって身体バランスは崩れる方向にいきます。縫合しても元のバランスには戻りません。ですので、手術は最終手段と考えるべきではないでしょうか。
- 施術について 既存の鍼灸やマッサージ、骨格矯正など手技と言われる手法はある意味「職人技」だと思います。施術者の経験と感覚、感性に起因するところが大きく、技術の個人差が出るところだと思います。鍼では刺す位置・深さ・角度・速度、マッサージでは摩るのか揉むのか指圧なのか・揉み方・指なのか手掌なのか・圧・角度・強弱・施す筋肉と施さない筋肉・一つの筋肉をとっても施す部分(近位遠位や外側内側)、骨格矯正では接触ポイント・圧・角度・速度・強弱、などミリ単位やコンマいくつ単位で効果が大きく変わります。しかしながら、結果が全てで、施術後の評価で判断することになります。
- 機械的アプローチ、機能的アプローチ 機械的アプローチは、力を使うことです。少し大げさに言うと、力づくですることです。マッサージ、手技による骨格矯正、ストレッチも力で筋肉を伸ばすことです。施術者の感覚に頼るところが大きいので、個人差があり、力加減や過度な負担を掛けてしまったりと技術的にも難しいところがあります。 機能的アプローチは、身体の仕組みや物理原理を利用することで、身体反射を利用したり、周波数を整えたりする手法です。機械的アプローチよりも、個人差が小さく精度も高くなると思われます。
- 肉体改造 来シーズンまでに肉体改造をすると、体重の増減、筋肉の付き方などを飲食物(カロリー、糖質制限、質)やトレーニングで調整します。体重が増えれば、パワーや飛距離が上がり、逆に瞬発力やスピードが落ちたりします。逆に体重が減ると、体が軽く動きにキレが出て瞬発力やスピードが増したなどと言われます。筋肉の付け方も、競技や役割によって上半身やどの部分に付け過ぎない方が良いなどと言われるケースもあります。一つ難点は、肉体改造が正解だったか不正解だったかは来シーズンならないと分からないことです。よく、肉体改造をして成績が落ちたりケガをしてシーズンを棒に振ることもあります。肉体改造をすることで身体バランス(周波数も)は当然変わります。身体バランスをチェックしながら、行うことが大切です。
- コンディショニング以外について
- 負荷の軽減 野球の例になりますが、投手であれば「球数制限(試合、練習)」「登板間隔を空ける」「連投を避ける」「負担の大きい球種を少なく・避ける」「正しいフォームに修正する」「DH制」「延長制限・再試合」「タイブレーク制」「道具・靴の開発」※「7回制の検討」など。近年は、MLBの後を追っており、申告敬遠、ピッチクロック、リプレー検証など試合時間の短縮や中断も投手には影響があると思われます。さすがに、肉離れ防止のため一塁までの全力疾走を控える、と言うのは少し違う感じがします。スポーツ選手が走れないとなると、スポーツ選手でないように思いますし、視点がずれてしまっています。どちらにしても、これらは根本解決の手段ではないですが、ケガ防止の助けにはなると思います。
- フォームの修正 関節の負担を減らしたり、パフォーマンスを向上したりするために動作解析で得られたデータや理想のフォームに修正することが行われています。身体バランスによって動作や軌道は変わりますので、悪いフォームでもその人にとっては普通の負荷の少ない動きの場合もあります。その場合、フォームが悪いからと良いフォームに修正すると、かえって負担が増えてしまい、パフォーマンスは上がったけれどその内ケガをしてしまった、というケースもあると思われます。フォームを変える場合は、身体バランスをチェックしながら実施することが大切です。
- ケアとトレーニング(鍛えること) 身体バランスが崩れたまま(歪んだまま)運動すればするほど、更に歪みを助長してしまいます。従って、コンディショニングで身体を整え、しっかり準備してから運動・トレーニングすることでケガは減るはずです。ケガをしない体づくりのために鍛える、と言うコメントを目にしたことがありますが、鍛えるとは強くすること、筋トレや反復練習を想像しますが、弱いからケガをするのではなく(そのケースもあると思いますが)、バランスが悪いから負荷が集中したり弾力性がなくなったりしてケガをすると考えられます。日常生活で左右対称に体を使うことはほとんどなく、スポーツでも左右対称に体を使うのは水泳の平泳ぎやスキージャンプなど少数で、他のほとんどが左右非対称に利き手足優先で体を使います。その結果身体が左右非対称に歪み、更に進行すると変形してしまうことも起こります。もしかしたら、一般的には身体は変えられないので、今の体の状態(これをその人の体の特徴ととらえて)で何とかしようと言う発想になっているかもしれません。体の歪みは軽減でき、骨の位置も変わり、足のアーチも作れ、足の大きさも左右同じにできます。ケアを見直してみる必要があるかもしれません。
新たな視点、量子的な視点:
私どもの施術 量子の振動技術や波の性質を使って、施術の精度を上げ、効率化することが可能となります。例えば、脊柱を整える時、骨盤(腸骨、仙骨など)→第5腰椎→第4腰椎…と骨の歪みを一つずつチェックすると矯正箇所を探すのに時間がかかります。量子技術を使うと、矯正箇所を瞬時に見つけ、矯正箇所が複数ある場合はできるだけ矯正箇所が少なくて済むように矯正の順番を見つけます。また、精度を上げるために、振動数・矯正箇所・矯正圧・矯正角度をミリ単位で決めて身体バランスをできる限り早く正確に整えるのが特徴です。
施術方法よりも、だれが施術するかが大切 全ての人・物が固有振動数(周波数)を持つことは先述の通りです。施術者も固有の周波数を発し、施術を受ける人も固有の周波数を発し、お互いが相手の周波数の影響を受けることになります。従って、鍼灸のA施術者とB施術者は発する周波数が違うので、それぞれから施術を受けた人の身体の状態・施術効果も異なることになります。
合う合わないの大切さ あの人とは波長が合うとか、あの人とは波長が合わない、と言う言葉を使ったり聞いたりすることがあります。人でも物でも、合う周波数では身体バランスが整い(歪みが減り)筋力が増します。一方、合わない周波数では身体バランスが崩れ(歪みが増し)筋力が低下し、結果ケガをしやすくなったりします。こうして見ると、周波数の合う人・物を味方につけ身に着けることが大切なことがわかります。良いメンタル(周波数)で人や物、チームに良い影響を与え、周波数の合う施術者、道具、靴を選択することが大切です。よく、勝負の世界ではゲンを担ぐ人がいます。色によって周波数が異なりその人に合う色があり、物の周波数はもちろん、ラインを左足から跨ぐなど動作も身体バランスの変化で周波数が変わるので、迷信ではなく理論的に説明がつきます。チームと選手の相性もあるとすると、スカウティングの仕方も変わってくるでしょうし、ポジションや打順などスターティングメンバーを決めること、監督を決める際にも活用されるかもしれません。
投手では、合う球種と合わない球種があり、合う球種だけのコンビネーションだと素晴らしい球が行ってバッターを抑えやすくなります。また、ボールの握りにも合う合わないがあって、例えばスライダーでも人によって合う握りと合わない握りがあって、合っているとキレや変化など素晴らしい球になります。一流選手は伝家の宝刀といわれるウイニングショットを持っていますが、自分の感性や感覚で知らず知らずの内に合う握りや球種などを獲得しているかもしれません。よく球種を増やしてストレートの質が落ちてしまった、と言う話も耳にしたことがあります。大リーガーS.R選手は、当初ストレートとフォークのコンビネーションで完全試合も成し遂げました。その後、WBCを境にスライダーを取り入れたかと思います。その影響とは断言できませんが、合わない球種で身体バランスが崩れ、その結果ストレートの球速が出なくなり、本来とは違うフォームで投げれば投げるほどバランスが崩れケガをしてしまった、と考えられなくもありません。 打者の目線を変えるため球種を増やす傾向にあると思いますが、球種を増やしたから必ず抑えられるわけでもありません。むしろ、自分に合った特定の球種の質を上げていく方が大事かもしれません。昔と今とは違うかもしれませんが、E.S氏は直球とカーブ、N.H氏は直球とフォーク、U.K氏もそれで活躍しました。その他にも、先発とリリーフのどちらが合うか、直球と変化球の球速差は何kmが適正か、なども知ることができます。
場、空間について あらゆる人・物から固有の波(周波数)が出ていて、それらがお互いに影響し合っていると先述しました。スポーツの現場では、データ化が進む中で相性も積極的に活用するチーム、指導者があります。これを、量子の場・空間という観点で見ると、競技場によって勝率の傾向があったりと、立地や競技場の形、大きさ、色なども関連があると推察できます。
投手と打者の勝負では、その空間内でお互いの周波数の優劣が勝敗を分けると思われます。身体を整えて良い状態に維持することは、ケガの予防だけでなく、勝負にも大きく影響するはずです。意識で周波数が変わると仮定すると、気迫とか、平静を保つとか、ボールに気持ちを込めるなど、根性論的な要素も必要なことが分かります。 また、ピッチャーマウンドやバッターボックスも一つの空間ととらえると、プレートの真ん中なのか一塁側・三塁側を踏むのか、バッターボックスのどの位置に立つかで状況が違うはずです。大リーガーO.S選手が、毎回バットを指標に使って立つ位置を決めているルーティンワークも理にかなっていると思います。また、野手のポジショニングを決めることにも応用できます。実際に、量子スポーツコンディショニングでは、どの位置に立つかで筋力の変化をテストして最適化しています。
評価法が大切:
いずれにしても、先述した色々な現象が起こることの確認や、身体がどの様な状態にあるかを確認する手段がないと、何が良くて悪いかの判断や選択もできないということになります。 そういう点で、「身体を整える技術」「維持する技術」「身体の状態を評価する技術」の3つが重要になります。
この項では、主に野球の例を使って説明してきましたが、他のどのスポーツにも同じ様な考え方で適用できます。
パフォーマンス向上:QSCがもたらす変化
パフォーマンス向上と、ケガの予防の対策は比例しており、ケガの予防の項の内容と同様に対策をしていきます。パフォーマンス向上には、主に次の3点が必要になります。
- メンタル 心の状態が身体に影響します。従って、メンタルをコントロールすることが重要となってきます。メンタルトレーニングが一般的ですが、コントロールできているかどうかを数値化などで判断することが難しく、結果で判断するか、どうしても抽象的な評価になりがちです。量子スポーツコンディショニングでは、筋力テストで具体的に見て体感し、どの様な心理状態の時に筋力が維持できたり低下したりするのか確認して、頭と体に記憶させていきます。 また、その人の考え方が影響するので、人間性の成長も求められます。プラス思考、プラスのイメージを持ち、感謝の気持ちを持ち、冷静さやワクワク感を持ち切り替えをする、そのために色々なエクササイズや呼吸法、ルーティンなどがあります。
- 身体バランスを整え、機能を正常化する 機能は、脳からの指令を伝える神経の伝達や、自律神経が調節するホルモン分泌や血流などの機能、目や耳などの器官、股関節や肩などの関節機能、筋肉の収縮など全てが相関し合っていることから、身体全体を整える必要があります。 潜在能力の最大値100とすると、身体バランスが悪いままでは80くらいには到達できても100にすることはできません。身体バランスを正しく整えれば、100に到達する可能性がでてきます。
- 良い状態を維持する 自分に合った物を身に着けたり、口から摂取したり、使ったりすることで身体バランスの崩れを防ぎます。 プレーに際しては、道具や靴、アクセサリー類、電子機器などがあります。また、構えやフォーム、動作、ポジショニングなども最適化していくことが大切です。 日常でも、サプリメントや水、寝具など、毎日口にする物や長時間使用する物です。 また、結論から言うと、身体バランスが整えば整うほど、合わない物の影響は受けにくくなります。
身体バランスとの関連/能力を最大限に発揮する
- 筋力:脱力できていることが大前提になります。 縮み代が大きいと収縮幅が大きく、関節可動域も大きくなり、より力が入ります。全身の沢山の筋肉が使え、左右差や内外差など強弱がなく、バランスが良いと最大限になります。力を入れていない状態で張っていたり硬い筋肉は、既に収縮していて縮み代が小さくなります。
- 動作:頭から足先まで連動していることが大切です。 脳、神経:反応速度に影響します 骨格:正しい位置(姿勢)にあることが大切です 筋肉:自律神経が正常で、血流が良く緊張がない 関節:可動域があり方向などスムーズなこと 感覚:視力・聴力など、器官への血流と神経伝達が大切です
- 体力:有酸素のクエン酸回路を活用してエネルギー効率を上げる※瞬発力は解糖系の回路 呼吸・心肺機能の正常化(酸素)と血流の改善(血糖) 毛細血管の増加と赤血球の増加(酸素運搬能力) 無駄な動きをなくし、少ない力で動作
- メンタル:自律神経の調整により安定、メンタルは筋力に影響
- その他:重心、噛合せ、足底アーチなどを整える
トレーニング・強化か、バランスかどちらを優先?
パフォーマンス向上のために、トレーニング、練習をしていると思います。
筋力強化 筋力トレーニングは、マシンを使う人、自重でする人、あるいは余計な筋肉をつけると動きの妨げになるとしない人もいます。昔はしない人がほとんどで、必要な筋肉は練習でつける(競技で使う筋肉を重点的に)という人もいますが、現代では実施する人が大半ではないでしょうか。どんな手法で、どこの筋肉を強化するか、適性があるはずです。競技によって使う筋肉が違うと言う人がいたり、違う競技をして筋肉痛になったなどあります。しかしながら、全ての動きは全身を使う(連動)が基本なので、身体バランスが良ければその様なことは少なくなるはずです。身体バランスが悪いと、筋トレをしても左右差や内外差が更に大きくなり、すればするほどバランスが悪くなる悪循環が起こります。
反復練習 できないことをできるようになるために新しい動きを覚えたり、フォームを安定、再現性の獲得など、反復練習をすることが大切です。身体に動作を記憶させることが大切で、時間が経過するとせっかく覚えた動きの記憶がなくなっていきます。そのため、定期的に再記憶をする必要があります。適正な間隔と、量(回数)が必要で、オーバーワークでの故障に注意することが大切です。意識してはじめて動くことになりますが、無意識で体が反応することは理想ではあります。近年、動作解析の技術も向上し、フォームの修正が行われています。ここで注意することは、修正前の動きが自分のやりやすい動き(今の身体バランスで)で負荷が少なく、いくら理想なフォームでもその人にとっては身体に負荷がかかる可能性があり、結果が良くなった反面ケガ故障のリスクを考慮する必要があります。正しい手法は、まず身体バランスを整え、それによって自然に良いフォームに近づき、意識して修正するのではなく無意識に修正されていき、当然結果も伴うことだと思います。
スピード・パワーか、コントロールかどちらを優先?
データテクノロジーの発達で、どの競技でも計測して数値化することが行われます。投手では、スピード、回転数、回転軸、回転効率など練習でも試合でも一球ごとに数値化され、選手自身は参考にして修正を加え、観戦者もそれを見て盛り上がるので、選手は更に数値の向上を目指します。トレーニング技術などの発達がそれを可能にし、高校生でもスピードでは引けを取りませんし、三振をとるのが醍醐味です。バッター目線は感覚的な要素もありますが、ピッチトンネルや、球速差、変化量や変化のタイミングなどの工夫もされます。打者も、飛球ごとにフライボール革命でバレルゾーン・打球角度が表示され、打球速度も表示されてバットの軌道やを調整し更にスイングスピードを上げようとします。打者では、ホームランが醍醐味となります。
一方、投手では、スピードがなくてもキレで勝負する、内外高低のコントロールや緩急を使って活躍する選手もあります。若い時はスピードが出るけれど、年とともにスピードが落ちて途中でスタイルを変えることは珍しくありません。投手で大切なのはコントロールと言われ、そのためにはある程度の球数を投げる反復練習(投げ込み)も欠かせません。打者でも、長距離打者と中距離打者があり、ホームランか三振かと言う確率の悪い打者もいれば、ホームランは少ないけれどバットの芯で打つ技術、バットコントロールに長けた三振の少ない打者もいます。長距離打者でもバットの芯でとらえた方がホームランの確立は上がるはずですが、芯を外しても力で持っていくということもあります。木製ではなく金属の高校野球で、飛ばないバットが採用されて飛距離が落ちてスモールベースボールを実践するチームが増えたかと思います。以前は打ち損じても大丈夫な様にパワーをつけていましたが、芯を外すと飛ばないので途端に芯で打つ練習をはじめます。芯に当たれば以前と飛距離が変わらないという声もあります。本来、野球の打撃は芯で打つスポーツのはずが、力に頼ったり道具の影響もあり、いつの間にか技術低下を招いていたという見方もできます。昔からパワーかアベレージかと区別する傾向があり、パワーとコントロールの両方兼ね備えた選手が数少ない三冠王です。そこには、タイミングや選球眼と言う要素もあると思います。身体的な特徴や能力、フォームなどで、投手であれば先発か抑えか、打者であれば打順や役割が決められていると思われます。近年、身体的に大きくなったこと、トレーニング技術や道具の開発、情報データなどで、球速が上がったり、球種が増えたこともあり(?)投高打低という現象が起こっています。ただ、もう一つの可能性として打者の技術低下の可能性も否定はできないと思いますので検証が必要でしょう。
本題に戻りますが、結論としては、スピード・パワーとコントロールの両方を得ることがベストです。現在は、スピード・パワー→コントロールの習得順序の様に思いますが、コントロール→スピード・パワーあるいは同時習得が良いのではと考えます。身体バランスを正しく整えることで、それが実現可能だと思います。
脱力の大切さ
どの競技にも共通していますが、スポーツはいかに脱力できるかが重要になります。筋肉が緩んだ状態を作ることで、瞬時に反応し、筋出力を最大限生かすことができます。現代スポーツを見ていて気になることは、力が入りすぎているのでは?と感じる選手が多いことです。このことが、もしかしたら技術の低下につながっている可能性はないでしょうか?恐らく、選手の皆さんは指導者から「肩の力を抜いていけ!」と言われた経験があるかと思います。もしかしたら、自分では力を抜いているつもりでも、実際には抜けていない、抜き方がわからない人もあるかもしれません。
施術をしていると、筋肉が過緊張していたり、力を抜く様に言っても「抜いています」とか「抜き方がわかりません」と言われる方がおられます。現代人は、空気や水も汚染され、食品添加物などの化学物質、スマホなどの電気製品が溢れかえり、精神的にも何かとストレスが多くあります。その影響か自律神経のバランスが悪い人が多く、脱力ができない一つの要因かもしれません。身体バランスを整えて対処する必要がありそうです。
QSCの評価方法:筋力テストの見える化
量子スポーツコンディショニングでは、最適化した身体・物を「筋力テスト」を使って評価していきます。次の様に、筋力テストを、「身体の優れたセンサー・測定装置」ととらえます。
(イメージ機構) 【体の部位・物の刺激 ⇒ 神経路 ⇒ 脳(判断) ⇒ 神経路 ⇒ 筋肉収縮の強弱(モニター)】
また、単にある筋肉の強い弱いをみるだけでなく、次の様な項目を評価していきます。
(確認できること)
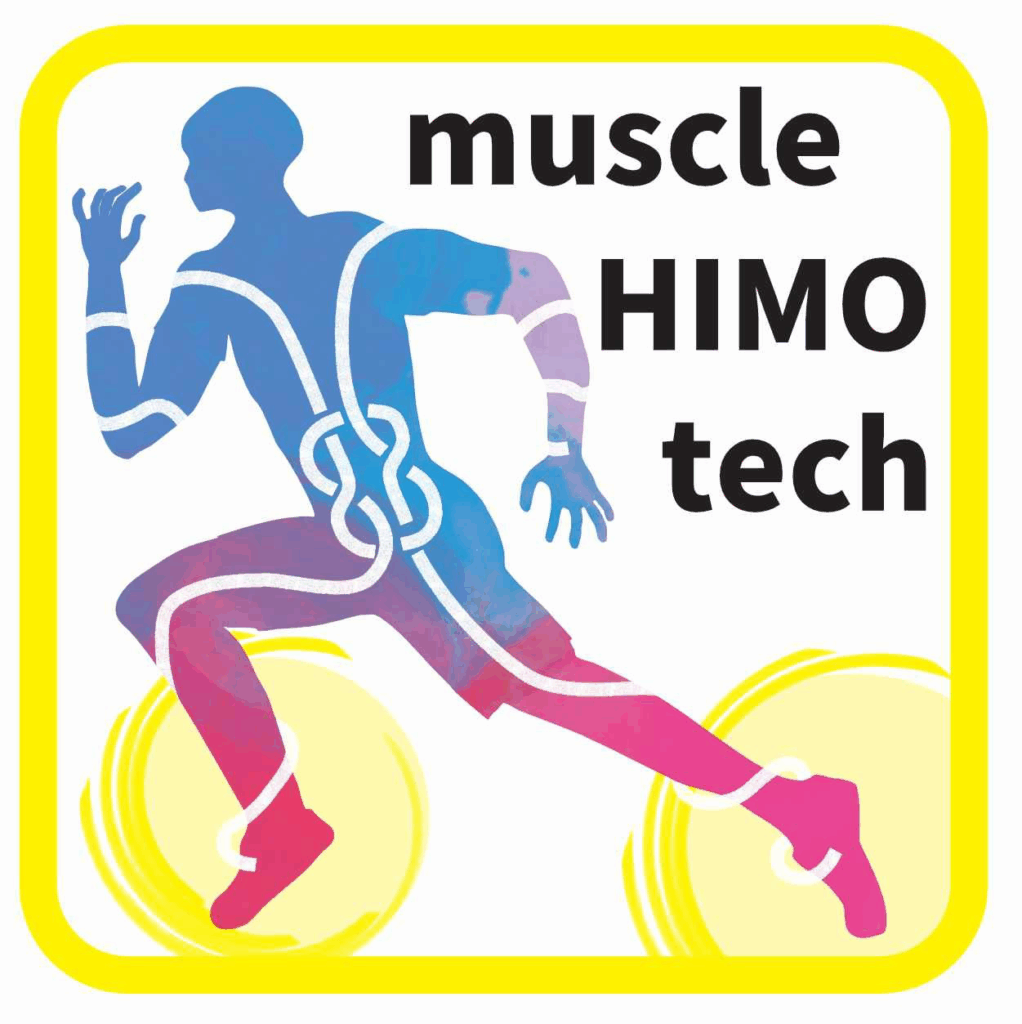
- 体の機能が正常かどうか(例えば、施術後に身体バランスが整ったかどうか)
- 歪みの有無(姿勢、骨格の位置)
- 噛合せ、重心、関節の状態など
- 意識の最適化
- 道具、靴、サプリメントなどの適正(材質・形状・大きさ・色など)
- 構え・フォーム・動作など適正
量子的には、意識が身体や周りの人・物にも影響を及ぼすとすると、検査者の意識を排除することが求められます。これについても、研究をしています。
筋力テストについて
「徒手筋力テスト(MMT)」は、病院等で筋力や神経障害の有無、治療やリハビリテーションの効果判定などを知る目的で、医師・理学療法士・作業療法士・歯科医師・それ以外の施術者などによって使用されています。
検査をする人の筋力、検査を受ける人の筋力、検査対象の筋肉の部位・症状の有無、他の筋肉の影響の排除、検査回数による疲れ、力を加える位置や方向などを考慮して評価する必要があります。
筋力低下の原因について
- 神経伝達の問題(a.疾患の場合、b.圧迫等の場合)
- 筋肉の問題(c.疾患の場合 d.主動作筋・拮抗筋・協力筋の動作不良) ※b.は、筋肉の収縮による骨の位置・関節の異常(歪み)。 d.は、骨の位置、使い方の偏り、外部からの影響などによる筋肉の収縮(硬い、張り)。 ※外部からの影響 → 電磁波、リング類(ネックレスなど)、カードの磁気、金属類など。その他、色々な物質、ストレスや意識など。
- 症状やケガの影響
バイ・デジタルO-リングテスト
医学博士の大村恵昭氏が考案した生理学的診断法です。筋力テストの一種で、検査筋として指の筋肉(母指と他のどれかの指)を使用します。指の筋肉は、日常一番よく使われる筋肉で、何回検査しても疲れの影響が少なく、疲れても早く回復し、大脳皮質の感覚領と運動領を最大限に代表しています。ある刺激に対して筋力が低下する機構は、「脳」をコンピューターの中央演算機構(CPS)と例えると、知覚神経の刺激→脊髄→中枢神経→脳と伝わった情報をCPSで判断し、モニター表示の代わりに指の筋力で表示しているイメージです。この精度は、コンピューターよりずっと高精度と言われています。このテストでは、体の異常部位や、歪みなど身体に関係するものだけでなく、食べ物や物の良し悪しも評価できます。ただ、テストを阻害する物(電磁波など)の影響を排除したり、検査者の力を加える方向など正しくテストを行うことが大切で、熟練が必要とされます。
新しい未来の形:量子技術の展望
量子技術を使って、より精度を上げ、効率化していくわけですが、量子理論が完全に解明されたわけではなく発展途上にあります。しかしながら、理論が完全に解明しないと活用できないわけではなく、結果が出ること・安全性・再現性などが得られれば今の理論レベルで実用化が行われ、後々に理論が解明されることとなります。量子技術も、分野によって活用の速度に差があり、スポーツ業界ははまだまだこれからの分野だと思います。ただ、いくら理論が解明され、測定で数値化しても、人間にしかできないことはあるはずで、生身の人間がプレイする限りは主体である「心・意識」「身体」を充実させることが土台・基礎だと考えます。しかしながら、今まで感覚をもとに使ってきた言葉「身体のキレ」「気合」「ゾーンに入っている」などは、「量子センシング技術」(磁気や周波数の微弱な変化を読み取る、小さくて観えない物の観測技術)で解明できる日がくると思われます。
量子のスポーツ分野への応用/今後の発展に期待
- 量子センサーによる生体計測 筋肉の動き、神経活動、心拍などの超精密なリアルタイムモニタリング →心臓や脳の微細な変化を検出し、交代やポジション変更、ケガの未然防止に役立てる
- 量子コンピューターによるパフォーマンス解析 複雑な運動パターン、戦術シミュレーション、筋骨格の最適化 →量子コンピュータを用いた多変数最適化でトレーニング計画を最適化
- 量子材料・設計を使った道具の進化 量子材料を使用した、軽量・高強度のウエアや道具の開発 →選手のパフォーマンス向上
- 「量子意識・脳」などを応用したメンタルトレーニング 意識の「ひらめき」「ゾーン状態」へ誘導、状況判断の強化 →脳波・呼吸などの制御と連動させ、意識をチューニングする
- 「量子場」の応用 チーム全体のエネルギー状態を「場」(空間)として捉え、それぞれの共鳴関係を調整 →競技場の相性、選手の状態、先発メンバー、ポジショニング、対戦相手との相性など ※現在はまだ黎明期だが、「個別最適化」「意識と身体の統合」「複雑状況での判断強化」という観点で非常に大きな可能性を秘めている
量子の代替医療への応用/今後の発展に期待
身体全体を「量子的なエネルギー場」としてとらえ、周波数の調整によりコンディショニングを整えてケガ予防やパフォーマンス向上に繋げる流れ
- 神経伝達の量子的調律 脳-脊髄-末梢神経系を「量子的エネルギー情報のパイプライン」と捉え、波動・周波数でチューニング →調整後に量子センサーで神経活動の整流化を測定して確認
- 量子共鳴による、非接触の調整 物理的な調整から、体に触れずにエネルギー的な調整へ →触れないアジャストメント(矯正)、刺さない鍼(鍼灸)など
- 量子センサーを用いた状態評価 肉体の構造だけでなく、身体のエネルギー場(Biofield)の状態を可視化・計測 →自律神経のバランス、脊柱上のエネルギーの流れ、などを波動的にスキャン
- 量子的「場」の連携 意識のエネルギーを「量子的操作要因」として訓練・活用する →施術家の意識・脳波状態や場のエネルギーが、クライアントの神経情報場に干渉・共鳴するという視点から、施術効果に強く影響する ※「量子スポーツコンディショニング」では、既に身体全体を量子のエネルギー場ととらえ、周波数を調整することでコンディショニングを整えています。調整後の確認を、現在は筋力テストを使って確認していますが、今後は、これを量子センサーで計測して数値化で証明していくようになると考えます。
量子スポーツコンディショニング(QSC)とは
QSCは、筋力に影響する4大ファクターを整える、トップアスリート向けの総合コンディショニング技術です。量子の「振動技術」と「波の性質」を使うことで、今までよりも「高精度」「高効率」な調整が可能となります。量子の導入が、今後のアスリートの「ケガの予防」と「パフォーマンス向上」を根本から変えていくことと思います。
(4大ファクター)
- 身体バランス
- メンタル
- 道具・靴・サプリメントなど
- 構え・フォーム・動作
※まず①身体バランスを整え、その状態を維持するために②~④を最適化します。
(評価法:筋力テスト)
- 今まで感覚で判断していたことを、「可視化」することで選手自身が理解できる
- 身体バランスのレベルをリアルに評価できる ※施術方法が異なっても公平に評価可能
- 筋力の強弱だけでなく、道具・靴・サプリメントなどの影響を評価
- 試したり使ってから判断するのではなく、事前に結果を予測し選定できる
(QSCのメリット・期待できること) 高精度・高効率に調整して最適化することで、
- ケガを未然に防ぐ(早期回復)、ケガを回避する能力の獲得(負荷分散、弾力性向上、血流向上)
- パフォーマンス向上、潜在能力を知る(自分の思う通りに動かせる、効率よく力を伝える連動)
- トレーニング・練習の効果を引き上げる
- 脱力しやすくなる(技術力の向上)
- 意識するのではなく、自然と無意識にフォームが整う(再現性の向上)
- パワー・飛距離・瞬発力と、バランス・コントロールを同時に獲得する
4つのステップ
身体バランス 量子技術を使って、周波数を調整することで施術の精度を上げ、効率化することが可能となります。身体バランスを整えることによって、身体機能が正常化していく、というシンプルでだれにでも適用(万能)できる手法です。 例えば、脊柱を整える時、通常は、骨盤(腸骨、仙骨など)→第5腰椎→第4腰椎…と骨の歪み(変位)を一つずつチェックして矯正箇所を探します。量子技術を使うと、矯正箇所を瞬時に見つけ、矯正箇所が複数ある場合はできるだけ矯正箇所が少なくて済むように矯正の順番を見つけます。また、精度を上げるために、周波数・矯正ポイント・矯正圧・矯正角度をミリ単位で決めて身体バランスをできる限り早く正確に整えるのが特徴です。
(施術内容)
- 全身バランス調整:姿勢、骨格位置、筋バランス、各神経伝達・自律神経調整、脚長差の調整。骨盤(仙骨・腸骨・恥骨・尾骨)~脊柱(腰椎・胸椎・頸椎)~頭蓋骨・顎関節~四肢まで、左右差、内外差、前後差をなくします。
- 脳脊髄液の循環、血液循環(血管・靭帯の弾力性向上、修復)、呼吸機能の改善。
- 足底のアーチ(内側・外側・横)改善、足の大きさ左右差調整。
- 自律神経の改善(ホルモン分泌、内臓機能、免疫など)。
(評価方法)
- 筋力テスト:筋力の変化をモニターして、身体機能の調整度合いを確認します。骨の位置・関節位置(歪み)、各関節の機能、噛合せ、重心なども評価します。
- メンタル 気持ちの持ち方などの心理状態で、筋力が変化することを体感し、頭と身体の両方で記憶・定着させます。チャンスやピンチで力を発揮して結果を出すには、身体バランスのベスト状態の維持(筋力の維持)、それを可能にする意識状態(プラス側)が必要です。その意識は、当然プラス発想ですが、そのためには練習による「自信」が鍵を握ります。これだけ練習・準備をしたのだから成功して当たり前という自信は、本番を想定した練習、高精度なコンディショニング、適切な筋力、反復による記憶、技術、道具に対する安心感などの裏付けからくるものです。また、人間性の成長(人間関係、コミュニケーション、度量、感謝など)も欠かせず、失敗も成功も含めて多くの経験をすることで獲得し、それが雑念を減らし集中力に繋がるはずです。
(体感・評価)
- 筋力テスト:筋力の変化をモニターして、意識による「筋力維持」「筋力低下」を確認します。
- 意識内容(プラス発想・マイナス発想)による、筋力変化を具体的に確認。
- プレー前、プレー中、プレー後の筋力変化、意識内容の関連を確認。
- 道具(靴)・サプリメントなど 身に付ける物、口から摂取するものによる、身体バランスの崩れを防ぐために、最適化をします。プレー中に身に着ける物はもちろん、日常でも長時間身に付ける物や、毎日使用するものは気を配る必要があります。トップアスリートほど、この細部の調整がコンマ何秒、コンマ何mmの勝負を分けます。また、基本的には合う物を選定して、購入することが大切です(合っていないものは調整します)。 ※身体バランスのレベルによって、合う物が変化することがあります。
(調整・評価)
- 筋力テスト:筋力の変化をモニターして、筋力が入るポイントを見つけます。
- 紐が付いている物:靴(靴紐の通し方・結び方の法則「マッスルひもテック®」で調整)、パンツの腰紐、グラブの紐、帯、胴着の紐など。
- 調節機能のある物:自転車のハンドル・サドル、バイクシューズのクリート位置、スキービンディング位置など。
- 持つ位置を調節できる物:野球バット、ゴルフクラブ、テニス・バドミントン・卓球のラケット、竹刀など。
- ボール:野球ボールの握り(直球、変化球)、ゴルフなどボールを選択できる場合、ボールの選定。
- サプリメント:体への適正・種類・量、消化吸収など内臓機能の評価。
- 筋力低下を起こす物:アクセサリー類、電子機器、湿布、テーピング類(合っていない場合)など、都度確認が必要です。
- 構え・フォーム・動作(空間、場) 手足の位置、スタンス、重心、手足の軌道、空間位置(ピッチャープレート位置など)などで、力の入るポイントを見つけていきます。この最適化によって、再現性の高い安定したフォームが可能となり、コントロールや飛距離・スピードの獲得に繋がっていきます。ここには身体バランスの状態が大きく関わっており、バランスが良くなるに連れて力の入るポイントが多くなり、より理想的なフォームや動作になっていきます。仮に、あるポイントで筋力低下が起こった場合は、余計な力が必要になって脱力ができず、プレーの精度・質が低下してしまいます。例えば、頸椎が左に歪んでいると首を左に向けた時点で筋力低下が起こり、右バッターは常に筋力低下状態です。
(調整・評価)
- 筋力テスト:筋力の変化をモニターして、筋力が入るポイントを見つけます。
- 特定の位置で構え、静止状態から始動する競技:野球投手(プレート位置、ワインドアップ・セットポジション、足を上げる位置、スタンス幅、リリースポイントなど)、野球打者(バッターボックス位置、スタンス、重心、手の位置、インパクトなど)、ゴルフ(スタンス幅、つま先の角度、重心、ボール位置など)、テニス・バレーボール・卓球など(サーブ時の位置、スタンス幅、重心など)、バスケットボールのフリースロー、サッカーのゴールキーパー、陸上短距離のスタートなど。
- その他、動きの多い競技、走るフォームなど、どの競技でも活用できます。
- 左右対称の競技:水泳平泳ぎなど。手足の筋力や軌道に差があるため、バランスが悪いほど方向修正に労力を使い推進力が低下してしまいます。身体バランスを整えることで、より推進力が増します。
サービス内容
- コンディショニング施術(身体バランス調整) 神経・骨格・筋肉を調整し(周波数調整)、バランスと出力を回復させます。筋力テストで姿勢、歪み、筋力、噛合せ、重心、足回り(足底アーチ回復、左右の足の大きさ調整)を評価します。
- パーソナルカウンセリング(メンタル、道具・靴・サプリメント、構え・フォーム・動作の最適化) 筋力テストで即時変化を体感しながら、各ファクターを最適化します。姿勢、歪み、筋力、噛合せ、重心、足回りのチェックに加え、靴紐の調整、最適な物の選定、競技ごとの構え・フォーム・動作チェックを行います。
※アスリートの皆様、所属チーム・企業様とのご契約形態に応じ、ご相談させていただきます。まずは一度、弊社の技術・効果をご体験いただくことをお勧めいたします。
適用例と期待できる効果
QSCは、野球、ソフトボール、ゴルフ、サッカー、水泳、バイク、マラソンなど、球技全般、陸上競技、冬季競技、武道といったあらゆる競技に適用可能です。
具体的な適用例と効果
- 野球、ソフトボール:
- スパイク、練習用シューズ、グラブの紐:筋力向上に繋がる通し方・結び方。
- 打者:バットの握り方(握り方、長さ)、スタンス、構え、重心、バッターボックス位置の最適化により、ミート率、飛距離、打球速度が向上。
- 投手:ピッチャープレート位置、ボールの握り(直球、変化球)、合う・合わない球種の選定により、コントロール、球速、回転数、回転軸、球の伸び、変化球の曲がりが向上。
- 守備:守備位置、スタンス、構えの最適化により、スタート、守備範囲、球際の強さ、送球の安定性、コントロールが向上。
- 走塁:リード幅、スタンス、構え、重心の最適化により、スタートが速くなり、スライディングの質も向上。
- ゴルフ:
- シューズの紐の通し方・結び方による筋力向上。
- クラブの握り(握り方、長さ)、スタンス、構え、重心、テークバック、ボール位置の最適化により、再現性、スイングスピード、コントロール、ミート率、飛距離、打球速度、スピン量が向上。
- サッカー:
- シューズ、パンツの紐の通し方・結び方による筋力向上。
- スタンス、重心、ボール位置、ポジショニングの最適化により、走力(持久力、スピード)、ボールスピード、コントロール、飛距離、球質が向上。
- 水泳:
- パンツの紐の結び方による筋力向上。
- フォームの安定、姿勢、腕の振り、足の蹴り、体力、方向性の安定が向上。
- バイク:
- シューズの紐の通し方・結び方による筋力向上。
- シューズのビンディング位置、バイクのサドル高さ・角度、ハンドル高さ・角度の最適化により、フォームの安定、姿勢、手腕の力、足の漕ぎ、体力が向上。
- マラソン:
- シューズの紐の通し方・結び方による筋力向上。
- フォームの安定、姿勢、腕の振り、歩幅、体力が向上。
するとは、腰や肩の張り・痛み・痺れといった外的なことだけでなく、自律神経の調整による内臓や目・耳など内的な機能、顎関節(噛み合わせ)や手足の小さな骨、肋骨や頭蓋骨といった細部まで整えることを意味します。
今後の展開
QSCは、量子理論のさらなる解明とともに進化し続けます。理論が完全に解明される前に、すでにその効果と安全性が確認されている技術は実用化され、後追いで理論が確立されていくものです。スポーツ業界における量子技術の活用はまだ黎明期にありますが、大きな可能性を秘めています。
量子のスポーツ分野への応用(今後の発展に期待)
- 量子センサーによる生体計測: 筋肉の動き、神経活動、心拍などの超精密なリアルタイムモニタリング。心臓や脳の微細な変化を検出し、交代やポジション変更、ケガの未然防止に役立てます。
- 量子コンピューターによるパフォーマンス解析: 複雑な運動パターン、戦術シミュレーション、筋骨格の最適化。量子コンピュータを用いた多変数最適化でトレーニング計画を最適化します。
- 量子材料・設計を使った道具の進化: 軽量・高強度のウェアや道具の開発が、選手のパフォーマンス向上に貢献します。
- 「量子意識・脳」を応用したメンタルトレーニング: 意識の「ひらめき」や「ゾーン状態」への誘導、状況判断の強化。脳波・呼吸などの制御と連動させ、意識をチューニングします。
- 「量子場」の応用: チーム全体のエネルギー状態を「場」(空間)として捉え、それぞれの共鳴関係を調整。競技場の相性、選手の状態、先発メンバー、ポジショニング、対戦相手との相性などに活用します。
これらは現在まだ黎明期にありますが、「個別最適化」「意識と身体の統合」「複雑状況での判断強化」という観点で非常に大きな可能性を秘めています。
量子の代替医療への応用(今後の発展に期待)
QSCでは既に、身体全体を「量子的なエネルギー場」として捉え、周波数を調整することでコンディショニングを整えています。調整後の確認は現在筋力テストで行っていますが、今後は量子センサーで計測し、数値化して証明していくことを目指します。
- 神経伝達の量子的調律: 脳-脊髄-末梢神経系を「量子的エネルギー情報のパイプライン」と捉え、波動・周波数でチューニング。調整後に量子センサーで神経活動の整流化を測定・確認します。
- 量子共鳴による、非接触の調整: 物理的な調整から、体に触れずにエネルギー的な調整へ(例:触れないアジャストメント、刺さない鍼)。
- 量子センサーを用いた状態評価: 肉体の構造だけでなく、身体のエネルギー場(Biofield)の状態を可視化・計測。自律神経のバランス、脊柱上のエネルギーの流れなどを波動的にスキャンします。
- 量子的「場」の連携: 意識のエネルギーを「量子的操作要因」として訓練・活用。施術家の意識・脳波状態や場のエネルギーが、クライアントの神経情報場に干渉・共鳴するという視点から、施術効果に強く影響します。
